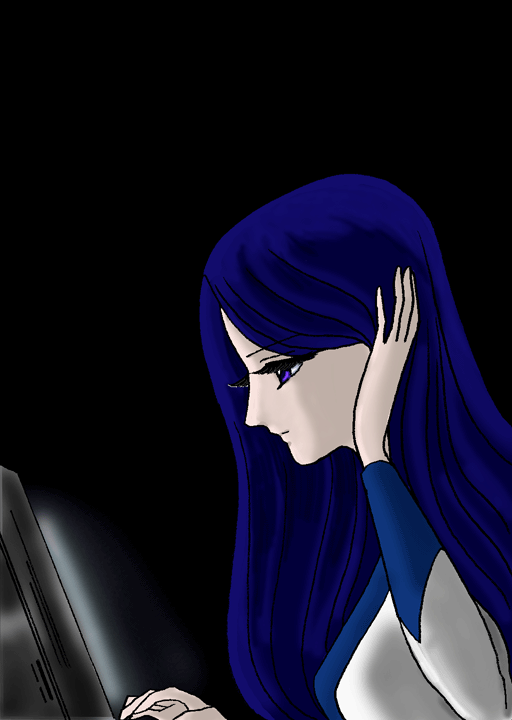| 第3章 銀河を抜けて /sect.3 |
|
シュルツの残存艦隊はついにヤマトを発見し、ビーム砲撃をかけてきた。ビームがヤマトを包むアステロイドに命中する。岩塊はビームを受け、砕け始めた。数発のビームが命中したころ、第一艦橋の真田のディスプレイに中央コンピュータ室からアステロイドの状況を示す図面が送られてきた。図面は左舷のアステロイドが弱くなりつつあることを示している。真田は振り向いて沖田に言った。 「艦長、このまま砲撃を受け続けていては危険です。岩盤を回転させて防御したいと思いますが」 沖田がうなずくのを見ると、真田は通信機のスイッチを入れた。 「艦外作業班は全員直ちに艦内へ退避せよ。五分後に岩盤を回転させる」 真田の立案したアステロイド・シップ計画は、単に補修作業時にヤマトをアステロイドで覆うというだけではなく、敵が接近した場合にはアステロイドをリング状にしてヤマトの周囲を回転させ、それによって敵のビームやミサイルを防ぐというものだった。シュルツ艦隊はヤマトに対して雨のようにビームを浴びせかけてきたが、回転するアステロイドに邪魔され、思うように命中させることができない。古代は必死にレバーを操作してアステロイドリングを操っていた。その時、艦内オール回線から緊張した声が響いた。 「こちら藤井です。敵艦隊がヤマトに特攻してきます」 島と古代は顔を見合わせた。敵艦隊は確かにヤマトに向かって接近しつつあるが、まだ特攻を思わせるような動きではない。島は振り返って沖田を見た。沖田は真田に顔を向けている。真田が言った。 「艦長、アステロイドの回転を解除して敵艦隊にぶつけます。よろしいですか」 沖田がうなずくのを確認すると、真田はレーダーに映った敵艦隊の座標を見ながら素早く数値を入力した。その時、突然敵艦隊が急加速した。艦影がみるみる大きくなる。 「うわっ、こっちに突っ込んでくるぞ!」 古代が叫んだ。真田は確信を持った声で言う。 「任せておけ」 真田がキーを押すと、ヤマトを包んでいたアステロイドはリングの形状から解き放たれ、意思を持つかのように一斉に敵艦隊をめざした。突如巨大な岩塊に見舞われたシュルツ艦隊の戦闘艦は、特攻しようと自ら加速していたことも災いして、次々にひしゃげ、爆発していく。宇宙空間にいくつもの巨大な炎の球体がひろがった。そして、周囲が再び闇に包まれた時、かつてその威容を誇ったシュルツ艦隊は既に跡形もなかった。 シュルツ艦隊の全滅を確認した後、沖田は技術班に十二時間の完全な休養を与えた。艦医の佐渡が、技師たちの健康状態が著しく悪化していると指摘したことと、真田の強い要求が、沖田を動かしたのである。それから三日後、冥王星会戦によって損傷したヤマトの艦体の修理は内外ともに完全に終了した。そして、沖田は各部署の長であるメインスタッフを中央作戦室に招集した。 中央作戦室は足元のスクリーンから照射される淡緑色の光にぼんやりと照らされていた。沖田の声が響く。 「そうすると、一回のワープは六百光年が限度だというわけかね」 「はい。それ以上の長距離ワープは波動エンジンやヤマトの艦体に損害を与えるおそれがあります。波動エンジンにエネルギーを蓄積する時間も考えますと、一回六百光年のワープを十二時間おきに行うのが、最も効率が良いと思われます」 真田は足元に映し出された航路図とデータを示しながら言った。島が腕組みをする。 「一日千二百光年ですか。片道百二十三日かかりますね。…今後戦闘でのロスがないとしても四か月だ。間に合うんでしょうか」 「真田くん、ワープの回数を一日三回に増やすわけにはいかんのか」 沖田の問いに、横から佐渡が口を出した。 「艦長、一日三回は、わしが止めたんじゃよ」 沖田が振り向く。佐渡はデータを手にしていた。 「この前のワープテストな、あの後で具合が悪くなった乗組員が大勢おったんじゃ。その連中を分析してみた。…ワープが人体に与える影響は軽視できんよ。短距離のワープでもあの始末じゃ。吐き気や眩暈はそのうち段々体が慣れるとしても、肉体に加わる負荷は相当なものだからな。六百光年のワープを日に三回もやったら、帰りは病人ばかりになるわい」 真田は佐渡の言葉が終わるのを待って沖田に言った。 「波動エンジンの出力のことだけを考えるのでしたら、一日三回までならなんとか可能です。ただし、定期チェックを頻繁に行って、金属疲労などが起きていないか、よく調べる必要があります。間隔が狭くなるほど、エンジンへの負荷も増えますので」 沖田はうなずくと一同を見回した。 「よし。当面は一日二回、八時と二十時に六百光年のワープをすることとする。そのうえで状況によってはワープ回数を増加させる。島、日程の計算をやり直しておけ。最初のワープは今から十五時間後、本日の二十時に行う。これよりそれまでの間、全乗組員に休暇を与える」 驚いた表情のクルーに向かって沖田は続けた。 「六百光年ワープするとなると、地球と交信できるのは今日が最後だろう。全乗組員に各自五分間ずつ地球との交信を許可する。相原、大至急交信順を決めて全員に通知しろ。それから森、展望室でパーティーの用意をするんだ。酒も許可する。地球とのさよならパーティーだぞ」 突然の休暇に艦内はわきたっていた。誰もが家族への交信を待ちかねてそわそわしている。展望室のパーティー会場は、冥王星艦隊を撃破した高揚感と、家族の顔を見られるという期待感から大変な盛り上がりを示していた。 一方、通信室では、通信班長の相原が忙しそうに出たり入ったりしていた。生活班の森雪も、通信補助を担当している関係上、通信室の前で交信予定の乗組員の整理に当たっている。ずらりと並んだ乗組員の氏名を一人ずつ確認していた雪は、やってくる真田を見た。真田はまっすぐに相原に近づくと一枚のメモを渡した。 「すまんな、相原。予定を狂わせて悪いが、このとおり変更しておいてくれないか」 「え、どうしたんですか、真田さん」 相原はメモに目を落とした。そして、驚いて顔を上げた。 「いいんですか、こんなことをして」 真田は笑った。 「そいつらはみんな、最近子供が生まれたばかりなのさ。俺は連絡するような近い身内がいないからな。よろしく頼む」 そう言うと、相原が止める間もなく、真田は歩き去った。雪はメモを手にして立っている相原に近づき、メモを覗き込んだ。…メモには、技術班の乗組員五人の名前と交信順位、そして真田の五分間の交信時間を各自に一分ずつ加算してやってほしいということが記載されていた。 「真田さんもだなんて…」 雪はそうつぶやくと軽く首を振った。キャビンが隣ということもあって、雪は緑と仲が良かった。今回の個人通信許可の報せを受けてすぐに、緑は雪のところへ来て、真田と同じことを頼んでいったのである。 真田は通信室から中央コンピュータ室に向かった。いま艦内で当直員がいるのはレーダー室と中央コンピュータ室だけである。第一艦橋はアナライザーが当直していた。 (皆に冥王星では無理をさせたしな。こんな時くらい全員に羽目をはずさせてやらないと…。それにしても、誰が当直だったかな) 真田がスイッチを押すと中央コンピュータ室のドアが開いた。その音にぱっと立ち上がる白い人影がある。真田の心臓が一回大きく鼓動した。…そこには、緑が胸に手を当てて立っていた。 「いいのか、こんなところで当直なんかしていて」 飛ぶように駆け寄ってきて用向きを尋ねる緑をもとの椅子に座らせると、真田はコンソールの前の椅子を引き寄せて逆向きに座り、背もたれに腕を乗せて言った。緑はきちんと両手を揃えて膝に乗せ、じっと真田の顔を見ていたが、その言葉を聞くと寂しそうに微笑んで目を落とした。そして、ゆっくりと言った。 「私には両親も、きょうだいもいませんし、近い親戚もみんな死んでしまいました。通信するような相手は地球にはいません。…それで、自分から当番の人に頼んで当直を代わってもらったんです」 「そうか…。すまん」 真田の沈んだ声に、緑はさっと顔を上げた。真田の顔をのぞきこむようにして、懸命に言う。 「いいえ、そんなこと…どうかご心配にならないで下さい。…あの、ここは私一人で大丈夫ですから、技師長はどうぞパーティー会場のほうへいらっしゃって下さい。きっと皆さんお待ちになっています」 真田は顔を上げた。そして、心配そうな緑の目を見ると、ほほえんで言った。 「いや。もうみんなかなりできあがっていたから、俺がいないほうが気楽だろう。それに、おれも通信は放棄してきたんだ。…家族がいないのはおれも同じでね」 緑はじっと真田の顔をみつめている。真田はそのひたむきな瞳をちらと見た後、さらに言葉を続けた。 「…両親はガミラスの爆撃で死んだし、姉さんはもっとずっと前、俺が手足をなくした事故の時に死んでしまった。だから俺も地球には連絡する相手がいないのさ。親友の古代守は冥王星会戦で戦死しているしな」 「古代守さんって…戦闘班長の古代さんのお兄さんですよね」 真田は驚いて緑の顔を見た。緑は記憶をたどるように言った。 「実戦部隊の見学の時、古代さんと一緒に第三ドックに行ったんです。古代さん、お兄さんに会うんだって言って喜んでいました」 緑はそこまで言うと、両手を握りしめて真田の顔を見た。 「技師長、ゆきかぜの整備のことでどうかご自分をお責めにならないで下さい。あの時、技師長はわざわざ参謀本部まで装甲の強化について交渉に行かれたじゃありませんか」 「どうしてそれを…ドックでおまえに会った記憶はないが」 「すみません。技師長がドックの電話で本部と交渉なさっているところを見てしまったんです。その後、山下さんとお話ししていらっしゃるところも。…私、あの時の技師長のお言葉を聞いて技術科に進むことを決めたんです」 真田は椅子から体を起こすと立ち上がり、後ろで手を組むと艦外モニター用の壁面ディスプレイを見た。そして、しばらくしてから言った。 「そうか。おまえのような女の子が汚れ仕事の技術班を選んだのはなぜかと思っていた。…しかし、なぜそんなことで?おれはただ装甲を二重にしろと言っていただけだ」 緑は立ち上がり、真田の背中に向かって言った。 「はい。…でも、ただ与えられた装備で指示どおりに戦うだけの人たちと違って、技師長はどうやったら勝てるかをお考えになって、そのために努力していらっしゃいました。それに、参謀本部に直接交渉に行くなんて、自分の保身を考えている普通の士官ではありえないことです」 真田は口元に苦い笑いを浮かべた。 「あの時は必死だったからな。しかし、参謀本部では全くとりあってくれなかった。…出撃する艦の数を減らすことなどできないというんだ。戦いは数じゃない、弱い艦をいくら出してもいたずらにやられるだけだ、と言ったが、無駄だった。しかし、冥王星会戦の大敗の後で、沖田艦長がおれをヤマトの技師長に指名してくれたのは、多分その時のことがあったからだと思う。指名の直後に、ヤマトの装甲のあるべき厚さについて相談を受けたよ」 真田は振り向いた。 「ガミラスに勝つために、俺もいろいろ考えていることがある。日常の任務の合間にしなくてはいけないから、楽な作業ではないが、良かったら手伝ってくれるか。…アステロイドの操作プログラムではいい仕事をしてもらった。特に、敵艦隊にぶつけるための設定が良くできていたよ」 緑の顔が輝いた。 「はい!私でよろしければ、ぜひお手伝いさせて下さい!」 「ありがとう。おまえに手伝ってもらえると随分助かると思う。とりあえず、今はヤマトのバルーンダミーを開発しようと思っているんだ。宇宙では遠近感がないから、二十分の一サイズでもうまく敵をだませると思う。ただ、敵のレーダーとの兼ね合いで素材について検討中でね。ちょっと見てくれるか」 真田はコンソールの前に座るとデータを呼び出した。緑が急いでその隣に座る。一瞬、石鹸のような甘い香りがふわりと漂った。その香りにふと横を見た真田は、いけないと思いつつも視線を離すことができなかった。…緑は頬にかかる髪をかきあげながら真剣に画面に見入っている。暗い部屋の中で、ディスプレイの光に淡く浮かび上がるその白い横顔は、たとえようもなく美しかった。
|
|
ぴよ
2001年09月26日(水) 00時59分40秒 公開 ■この作品の著作権はぴよさんにあります。無断転載は禁止です。 |
|
| この作品の感想をお寄せください。 | ||
|---|---|---|
| 続き:私ならこの時点でもう緑に惚れています | メカニック | ■2011年06月20日(月) 23時57分11秒 |
| 最後のくだりは読んでいる私でさえ緑から目を離せなかったから隣の真田さんはもっとでしょう。私なら | メカニック | ■2011年06月20日(月) 23時55分59秒 |
| 心に傷を負った者同士の交歓。ワープの設定。お見事です。佐渡先生がいいな。ヤマト本編をみてるようでたのしいです!バルーンダミーも懐かしいですね!! | 長田亀吉 | ■2001年09月26日(水) 08時05分14秒 |