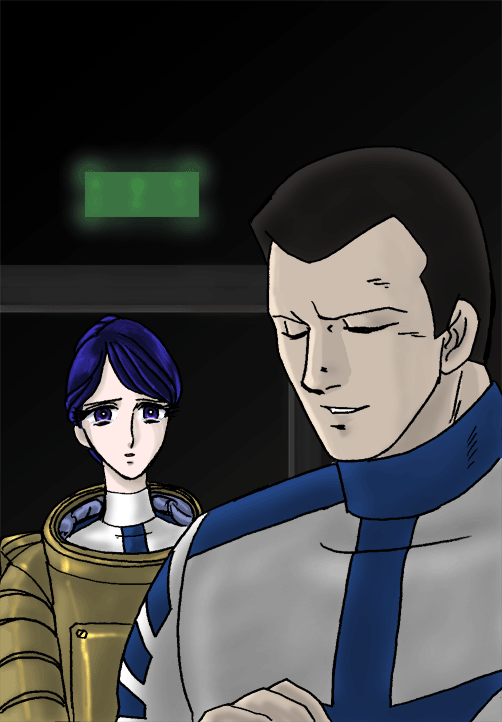| 第3章 銀河を抜けて /sect.2 |
|
敵の艦影はみるみるうちにその数を増やし、大艦隊となった。砲撃を避けるようにとの真田の進言で、ヤマトは右舷前方にあったアステロイドベルトに進入し、その回転周期に速度を合わせて姿を隠した。沖田は艦長室に戻っていく。…真田はあらかじめ作ってあった作戦計画書を第一艦橋でプリントアウトすると、艦長室に向かった。アステロイドシップ計画について説明しなくてはならない。 真田が設計室に戻った時には警報が鳴ってから三時間が過ぎていた。沖田はアステロイドシップ計画の利点を理解し、作戦許可を与えてくれたのである。設計室のドアを開けた真田は、コンソールの上に一枚のディスクが乗せてあるのに気づいた。ディスクにはメモが添えてある。真田はメモを手にとった。 『差し出たこととは思いましたが、プログラムをコピーして、残りの作業をしてみました。もとのデータはそのままハードに入っています。なお、アステロイド装着を解除する時、敵にアステロイドが衝突するように飛散させてはどうかと思い、そのプログラムも付け加えておきました。もしご不要でしたら消去して下さい。デバッグは済んでいます。どうか少しでもお休みになって下さい。藤井』 「俺と全く同じことを思いつくとはな…」 真田は微笑んでそう呟いた。ディスクを挿入する。現れたプログラムを確認するにつれ、真田の顔に感嘆の表情が浮かんだ。 (たいしたものだ。このまま手を加えずに使える。すぐにアステロイドを装着できるな) 真田はディスクのデータをコンピュータに落とし込み、立ち上がった。 緑はシャワー室から出て、洗った髪をタオルで拭いていた。隊員服は自動ランドリーに入れてあるので、ゆったりしたTシャツをワンピースのように着ている。熱いシャワーでほてった体には、風のとおるTシャツが心地よかった。体の芯から疲労がわきあがってくる。ふと鏡を見ると、目の下に濃い紫色のくまがくっきりと浮き出していた。 (こんなひどい顔で技師長とお話ししていたなんて…。交代まであと二時間くらいあるから、寝ようかしら) 鏡の中の自分の顔に、真田の顔が重なる。警報が鳴る直前、設計室で真田が肩に手をかけた時、緑はそこから全身に電流が走ったように感じていた。その時のことを思い出すだけで頬が熱くなる。 (いけない、私がこんな気持ちでいるのがわかったら、きっとご迷惑になるわ。…今までのようにお話しできなくなってしまう) 電子音を立ててランドリーが止まった。きれいになった隊員服を着て、濡れた髪をきりりとまとめ上げ、緑は背筋を伸ばした。 (とにかく技師長に休んでいただかなくては。そのためには、一刻も早く補修を終わらせるのが先決だわ) その時、スピーカーから真田の声が響いた。 「技術班に告げる。休憩時間を削ってすまないが、敵艦隊が接近しているため、作業開始を繰り上げる。一班と四班は三十分後から艦外作業とする。至急準備にかかれ。二班は完成した装甲板の積み込み終了後、同じく艦外作業。三班はいったん艦内に戻り、エアー交換後一時間休憩、その後艦外作業を再開せよ。三班のうち二名は中央コンピュータ室を担当のこと。補修担当区域は、一班を左舷、四班を右舷、二班を後部上甲板及び砲塔とする。三班は二班をサポートせよ」 緑は待機ボックスに向かって走りながら、唇をかみしめていた。真田の声を聞いただけで胸が痛い。尊敬と憧れだと思っていた真田への気持ちが、冥王星での戦闘以来、抜き差しならない深いものに変わりつつあるのが自分でもわかった。これまで自分に交際を申し込んできた同期生たちの気持ちが、いまになってわかる。あのころはどうして皆が悲しそうな目で自分を見つめるのか、ただ不思議にしか思わなかった。どの同期生とも単なる友達としてしか会話してこなかった自分の無邪気な残酷さが、いまさらながらに胸に迫る。 (みんな、本当にごめんなさい。…知らなかったの、こんなにつらいものだなんて…) 真田は第一艦橋の古代の席の後ろに立ち、じっと前方を見つめていたが、周囲のアステロイドの状況にうなずくと声を上げた。 「よし、反重力感応器、発射準備」 古代が発射装置のレバーに手をかけ、復唱する。 「反重力感応器、発射準備よろし」 「発射角上下、四〇」 「上下四〇。了解」 「発射!」 真田の号令とともに、第一砲塔が火を噴いた。発射されたカートリッジが前方に高く上がり、炸薬によって内部の反重力感応器が球形に広がり、さらにその中から小さな反重力感応器がばらまかれた。それは、まるで打ち上げ花火のような光景だった。…ヤマトの周囲に広がった反重力感応器は、次々とアステロイドに突き刺さっていく。真田は手元の携帯スクリーンを見ていたが、やがて顔を上げた。 「よし、もういいだろう。修理班、配置につけ。これより岩盤を装着する。装着終了後、直ちに作業を開始せよ。…岩盤、装着」 「岩盤、装着」 古代が復唱し、レバーを動かすと、ヤマトの周囲のアステロイドが動き始めた。反重力感応器は予め設定された位置へと岩盤を動かしていく。やがて、ヤマトは第一艦橋と艦首の一部、そして艦尾を残してすべて岩盤に覆われた。艦体と岩盤の間には五メートルほどの空間がある。 「技術班、作業にかかれ」 命令を出した後、真田は振り向いて艦長席の沖田を見た。 「艦長、自分も艦外に出て作業指揮に当たりたいと思います」 沖田はうなずいた。 「うむ。…ただし、ガミラス艦隊が砲撃してきたら、きみは艦橋に戻りたまえ。その後の作戦指揮もある」 「分かりました」 真田は艦橋を駆け出していった。古代がぼやく。 「それにしてもみっともない姿だよな。ヤマトが岩でごてごてだぜ」 座席にもたれていた島がいさめた。 「しょうがないだろ、修理のためなんだから。守りも完璧である必要があるんだぜ、古代。修理にはまだまだ時間がかかるみたいだからな」 二人の会話を聞いて、レーダーを見ていた雪がつぶやいた。 「真田さん、すごく顔色が悪かったわ。また艦外なんかに出て大丈夫なのかしら。特攻隊からこっち、全然寝ていないみたいだし」 古代と島は黙り込んだ。 真田はハードスーツを着るとエアロックに向かった。ヘルメットのフェイスプレートを下ろすと、ずっと続いていた頭痛がまたひどくなった。スーツの胸のスイッチを押して伸びてきたストローをくわえる。ハードスーツには簡単な飲料を二種類セットしておくことができた。 (あまり多用するとさすがにまずいが、まあ仕方ないか) 覚醒作用のある薬物を混ぜたエネルギー飲料は、苦い味がした。…この薬物は真田が宇宙戦士訓練学校時代に開発したもので、論文を発表した時はかなりの反響があった。長時間の戦闘が続くことの多い宇宙の戦いでは、副作用のない薬物への需要が多かったからである。この薬はそれまでの薬物に比べると副作用が格段に少なく、軍での正式な採用が有望視されたが、短期間に連用すると心臓に悪影響を及ぼすという欠点から、結局兵士への配布は見送られたという経緯があった。 エアロックのランプが緑に変わった。外へ出ようとスイッチを押した真田は、ふと目に入った自分の腕から目をそらした。なぜか緑の顔が浮かぶ。 (おれは普通の体じゃないしな。あと一回ぐらいは心臓ももってくれるだろう) 自嘲気味にそう呟くと、真田はエアロックの端を蹴った。 右舷と上甲板の作業状況のチェックを済ませた真田は、左舷のPブロックに近づいた。 一班は最も整然と作業に当たっていた。技師たちはごつごつした岩盤の内側で新しい装甲板を艦体に溶接している。台車の上で装甲板の受け渡しをしていた山下が振り向いた。 真田はヘルメットを山下に接触させた。 「技師長、艦橋にいらっしゃらなくていいんですか」 「大丈夫だ。…すまなかったな、少しでも寝られたか」 「はい。警報が鳴ったんで、こりゃやばいと思ってすぐ寝ました。みんなも寝させてあります。…緑だけは女の子なんで確認できませんでしたが」 「たぶんあいつは寝ていない。俺の手伝いをしてこのプログラムを組んでいたんだ」 山下は真田からヘルメットを離し、装甲板の番号を確認すると、近づいてきた大石に渡した。そして、振り向くと真剣な表情で真田を見た。 「技師長、ここは私が責任を持って気密チェックまで終わらせます。どうか艦内に戻って少しでもお休み下さい。α−4は心臓に害があるからやめておけとおっしゃったのは技師長じゃありませんか」 山下は他の技師にも聞こえることを承知で無線を使っていた。真田もやむなく無線のスイッチを入れた。 「今回はまだ三回しか使っていない。心配するな、俺の体のことはおまえだって知っているだろう」 「そういう問題じゃありません。ついでに緑も艦内に連れて帰って下さい。七五時間以上も休んでいないやつに艦外作業なんてやらせられませんよ」 山下は強硬だった。作業を続けていた技師たちが無線から聞こえる二人の会話に振り向く。緑の隣で溶接機を使っていた吉川は、緑が動揺していることに気づいた。それに追い打ちをかけるように山下の声が飛ぶ。 「吉川、そこの溶接はおまえだけでやれるな」 吉川は急いで答えた。 「はい、大丈夫です。緑は艦内に帰してやって下さい」 「吉川さん…!」 緑は溶接機を持ったまま抗議の声を上げたが、吉川は素早く緑にヘルメットを接触させた。 「戻れよ。お前が戻らないと、技師長も休んでくれないぞ。…やっぱりこのプログラム、休憩時間中におまえと技師長で組んだんだな」 緑は目を伏せるとヘルメットの中で小さくうなずいた。その時、真田の声が聞こえた。 「緑、聞いたとおりだ。艦内に戻れ。…中央コンピュータ室に臨時配置する。アステロイドの状況をチェックして第一艦橋に報告するんだ」 エアロックの中で真田は黙って前方を見ていた。緑は真田の後ろからその背中をみつめていたが、警告灯がグリーンに変わるとすぐにヘルメットを外し、ためらいがちに声をかけた。 「技師長、α−4を三回もお使いになっているって本当ですか」 真田はヘルメットを外しながら振り向いた。 「ああ。だからおれのことは心配するな。あと十時間やそこらは楽にもつよ。おまえは中央コンピュータ室に行く前に三時間だけキャビンで寝てこい。これは命令だ」 「私は大丈夫です。技師長こそキャビンでお休み下さい。ガミラス艦隊の様子が変わったら、すぐにお知らせします。こんなことをなさっていて、もしものことがあったら…」 緑の目にはうっすらと涙が浮かんでいた。それを見た真田は視線をそらし、緑に背を向けるとウエストのファスナーを外し、ハードスーツを脱いだ。…真田はスーツを床に置くと自分の両手を見た。そして目を閉じて拳を固く握りしめた後、笑顔を作って振り向いた。 「余計な心配をさせてすまん。お前にはまだ話してなかったんだな。…おれは日頃から、普通の人より心臓の負担が少ない体なんだ」 緑はハードスーツを着たまま、じっと真田を見上げている。涙に濡れた黒い瞳を見ると、その後の言葉を口に出すのに大変な努力が必要だった。真田は自分の中の何かを断ち切るように言った。 「おれの手足は作り物なんだ。…子供の頃の事故で全部切断してしまった。だが、そのせいで心臓は楽をしているのさ。だから安心してくれ。α−4を三回使ったぐらいではどうということはない」 緑を自室へ戻らせてから真田は第一艦橋に向かった。真田から手足のことを聞かされた後、緑は大きな目を一杯に見開いて、悲しそうに真田を見つめていたが、それ以上何も言わず、黙って真田の命令に従った。真田は艦橋に向かうエレベーターに乗ると壁にもたれ、目を閉じた。悲しそうな緑の表情が胸に灼きついている。真田は自分に言い聞かせた。 (これで良かったんだ…。十も年下で、しかも直属の部下だぞ。あいつだって、何もかもわかればおそらく) それ以上考えるのをやめて、真田は目を開いた。エレベーターのドアが開く。真田は大股に右舷の自分の席に向かった。
|
|
ぴよ
2001年09月25日(火) 01時29分03秒 公開 ■この作品の著作権はぴよさんにあります。無断転載は禁止です。 |
|
| この作品の感想をお寄せください。 | ||
|---|---|---|
| やはり緑が真田さんへの気持ちに気付いたところの件は何回読んでも切なくなります。私も緑にこの位想われてみたいです。 | メカニック | ■2010年02月02日(火) 15時16分23秒 |
| (みんな、本当にごめんなさい。…知らなかったの、こんなにつらいものだなんて…) ここの部分を読んだとき涙が出そうになりました。 | メカニック(続き)↓ | ■2009年05月31日(日) 20時02分56秒 |
| 初めて読ませていただきました。 | メカニック | ■2009年05月31日(日) 19時55分09秒 |