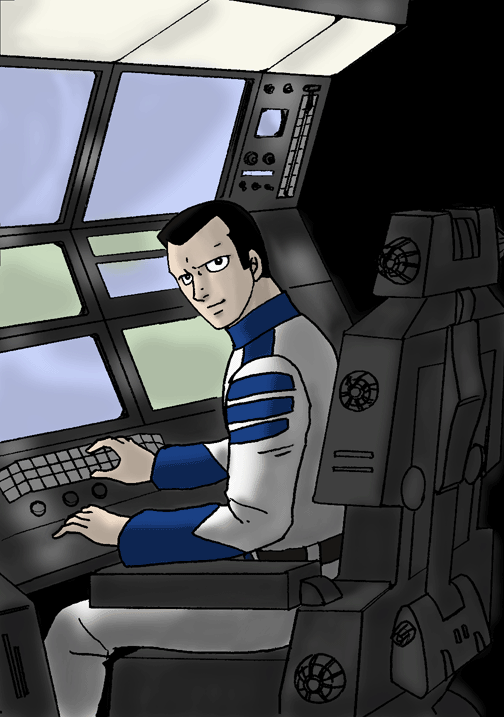| 第3章 銀河を抜けて /sect.1 |
|
低速で航行を続けるヤマトの周囲にレーザーカッターの散らす光がまるで蛍のようにきらめいている。できるだけ早く補修を完了させるようにとの沖田の命令で、技術班は冥王星を発進した後も総力態勢で補修作業を続行していた。 「技師長、やはりPブロックの第一装甲板が足りません。…三班に言って補充してもらわないと」 台車を調べていた山下の言葉に、真田は時計を見た。 「もうそろそろみんなのエアーも切れる。これで作業交代にしよう。区切りのついた者から艦内に戻れ。後は三班と四班にやらせる。艦内に戻ったら全員三十分間休憩だ」 真田の言葉を聞いた一班と二班の技師はほっとした表情を浮かべた。ハードスーツを着て宇宙空間に出ている間は、額の汗を拭くこともできない。二時間ごとのエアー交換の際にわずかな休憩をとっただけで、もう八時間以上も艦外作業を続けているため、技師たちの疲労は頂点に達していた。エアロックに戻った後、酸素が充満するのを待ち切れず、警告灯がグリーンになる前にヘルメットを外す若い技師もいる。緑はエアロックにライトがつくのを待って内部を見回した。…そこに真田の姿はなかった。 (技師長、まだ艦外にいらっしゃるんだわ) ハードスーツのヘルメットの受信回路を調整すると、真田が工場にいる三班の技師に装甲板の追加製造を指示している声が聞こえた。真田はヤマトを外部から点検してコンピュータの把握しきれない破損部分や作業進度をチェックしている様子だった。緑はハードスーツのバックパックを素早く交換すると、再び艦外に出た。真田はバーニアでPブロックの破損箇所に沿って上昇している。緑は真田のいる方向をめざしてバーニアを噴射しながら回線を開いた。 「技師長!」 専用回線で呼ばれた真田が振り向く。緑は真田のそばまで行くと逆噴射を使って停止した。 「どうした、緑。…艦内に戻って休憩していろ」 携帯用端末を手にした真田はそう言うと再び上昇を始めようとした。緑があとを追う。 「破損箇所の再チェックをなさるのでしたら、お手伝いさせて下さい」 その言葉に、真田は脚で反動をつけて停止した。しばらく黙って緑を見ている。こうして近くで見ると、真田の顔は疲労にくまどられていた。…やがて真田は口を開いた。 「おまえはずっと艦外作業をして疲れているだろう。あと三十分で四班の者が艦外に出て来る。その連中に手伝ってもらうよ。休んでこい」 緑は懸命に言った。 「これぐらい、たいしたことはありません。それに、いまは休憩時間中ですから、私がお手伝いしたほうが補修作業に支障が出ません。…お願いします。どうかお手伝いさせて下さい。技師長こそ、ガミラス基地に出発してから、これまで全然お休みになっていません。お一人で全部チェックなさるなんて、無茶です」 必死に言いつのる緑を見ているうちに、真田の疲れた口元にかすかな笑みが浮かんできた。真田は緑の肩に手をかけた。 「ありがとう。それじゃ、右舷を頼む。…ビームコーティングの損傷状況と、第一装甲板のめくれ上がりの度合いを調べてくれ。コバンザメの溶接をはがすまで分からなかったんだが、破損箇所の巻き上がりのせいで、コンピュータの指示する損傷部位だけの交換では済まない部分が多いんだ。おかげで装甲板の追加製造を待たないと補修が進められない。…携帯端末は持ってきたんだな」 「はい!」 「それじゃ、そこの図面2に交換の必要な箇所を原因別に分けて書き込んでいってくれ。そうすれば三班がそのデータをもとにすぐ装甲板の製造を始める。本当をいうと、こうしている間にもガミラス艦隊が戻ってくるんじゃないかと気掛かりなんだが、みんなの体力ももう限界だからな。艦内の作業も資材待ちのところが多いんだ。…そういえば、あれから、何か見たり、感じたりしたことはないか」 緑は真田の目を見つめたまま、黙ってかぶりをふった。真田は笑って緑の肩を叩いた。 「なら、大丈夫だ。今のうちに急いで片づけよう」 コバンザメを除去した後、艦外からのチェックによって判明したデータに基づいて、真田は新しい補修計画を立てた。冥王星空域での戦闘開始から既に六〇時間以上が経過しており、不眠不休で重労働を続けていた技師たち全員を作業に付かせるのはもはや無理だった。真田は装甲板の製造が完了するまでの十二時間の間に、技師たちを二班ずつ六時間交代で眠らせることにした。汗まみれになり、疲れ果てていた技師たちは、シャワー室に駆け込んだ後、急いでキャビンに戻っていった。 一班は装甲板の製造を三班から引き継いでいたため、休息は後番となっていた。古賀は完成した装甲板を台車へと移動させながら吉川に向かってぼやいた。 「なんで技術班ばかり戦闘中も戦闘後も休みなしなんだろうな。…知ってるか、戦闘班のやつらなんて、戦闘待機の時以外は寝放題なんだぜ。戦闘の時に一番危ない所にいるのだって俺たちなのに。ハードスーツいっちょうでミサイルとビームだらけの艦外に出てるんだからな」 そばにいた大石が振り向いた。 「じゃあ、戦闘班に志願するか、古賀。…いつでも俺から技師長に言ってやるぜ」 古賀は慌てて手を振った。 「と、とんでもない。おれはそんなつもりで言ったんじゃありませんよ」 空の台車を運転して近づいてきた一班Cの青木が笑う。 「なんだ、がっかりさせるなよ。おまえが戦闘班に移ったら、俺をD班に入れてもらうよう頼もうと思ったのに。一班Dは競争率高いんだぞ」 その会話を聞いていた山下は、装甲板積込み用のクレーンを操作しながら言った。 「青木、C班を出たいなら、いつでも変えてやるぞ。…そのかわり、お前の欠員分として、緑をC班にもらうからな」 「班長!」 「せっせと働けよ。まじめにやらないと緑を他の班へ移されちまうぞ。お前ら、よその連中が技師長にどういう陳情出してるか知らないだろう。…ほれ、アームを下げろ。予定より早く製造を終わらせるんだ。あと四時間で休みだぞ。頑張れ」 緑は山下の指示で自動ラインのコントロール席に座ってミサイルの製造を管理していた。その時、ディスプレイに星印のついたメッセージが入った。 『3号ラインのミサイル製造は中止する。1、2号のラインをスピードアップして間に合わせてくれ。3号では、これから送るデータに基づいて別の装置の製造を開始する。個数は三百個だ。百個ずつカートリッジに詰めて主砲で発射するから、その準備も頼む。今からデータを送る』 間もなく、ディスプレイに詳細な図面と自動製造用プログラムが現れた。 「これは…超小型の外部誘導式反重力感応器だわ」 そうつぶやくと、緑は真田のいる設計室の方向に目をやったが、すぐに思い直してキーボードを叩き始めた。1、2号ラインの速度調整と、3号ラインの資材の設定変更を急がなくてはならない。 作業交代から五時間半が過ぎた。緑たちの作業を引き継ぐ予定の二班の技師は、交代時刻までまだ三〇分以上あるというのに、早くも工作室にやってきはじめていた。緑は完成した反重力感応器を主砲用のカートリッジに詰めていたが、二班の技師たちは工作室に入ってくるなり緑の周囲に群がった。 「重たそうじゃないか。かわいそうに。俺がやるよ」 「いえ、皆さんはまだ休憩時間中ですから、どうぞお休みになっていて下さい」 「いいんだって。五時間寝たらすっきりしたよ」 「そういうこと。…なあ、これ、発射した後で、ぱっと広がるように詰めりゃいいんだろ?」 「はい。あの、でも…」 緑の当惑をよそに、青年たちは陽気だった。鼻唄まじりに作業にかかる。 「何だろうな、これ。アンチミサイルかしらん」 「規格品じゃないもんな。技師長の発明した新兵器か?」 緑はにっこりと笑ってうなずいた。 「すごく小型ですが、反重力感応器です。一個当たりさらに十個の小型感応器が詰めてあるんです。…主砲で何かに打ち込んで、艦内から操作して動かすんだと思います」 青年たちは顔を見合わせた。 「何を動かすんだろう?」 「敵の戦艦…じゃないよな、まさか」 「なあ、緑。これ、カートリッジに詰めた後、どこの主砲に配置すればいいのか分からないぜ。技師長に聞いてきてくれないか。そのついでに用途も教えてもらってこいよ」 「でも、私はまだ作業時間中ですし…」 ためらう緑の背中を、後ろから近づいてきた山下が叩いた。 「緑、行ってきていいぞ。ここはもう二班が引き継ぐそうだ。…みんな、時間前に持ち場に来るとは感心だな。感心ついでに頼ませてもらうが、三人ほど装甲板のほうに来てくれないか。残りの作業の引継ぎをしておきたいんだ」 山下は二班の技師に向かってにやっと笑った。 緑が設計室に向かって歩いていくと、コップやピッチャーを乗せたトレイを持って、アナライザーがやってきた。アナライザーはきょろきょろとあたりを見回している。 「どうしたの、アナライザー」 声をかけると、アナライザーはピコピコと賑やかな電子音を立てながら近づいてきた。 「ミドリサン、イツモキレイデスネ。サナダサンハ、ドコデショウ」 緑はくすっと笑った。 「アナライザー、お世辞は挨拶とは違うのよ。…技師長なら設計室だと思うけれど」 「ソウデスカ。スミマセン。司厨長カラノ、サシイレデ、ヤマト農園ノ、フレッシュトマトジュースヲ、当直ノミナサンニ、オモチシタノデスガ」 「一班と二班の当直の人たちはあっちよ。もうすぐ当直交代だから、急いだほうがいいと思うわ。…これから技師長のところにおうかがいするから、技師長の分は私がお届けしておきましょうか」 「オネガイシマス」 「失礼します」 控えめにノックした後、声をかけて中に入る。…設計室には大型コンピュータがあるため、室温が低く設定されていた。ひんやりとした空気が体を包む。真田が肩ごしに振り向いた。 「トマトジュースをお持ちしました。司厨長からの差し入れだそうです」 「ありがとう」 真田はコップを受け取ると、一気に飲みほした。緑は空のコップを受け取りながら尋ねた。 「技師長、反重力感応器の製造が終わりました。配置は何番の砲塔にすればよろしいでしょうか」 真田は椅子を回して緑のほうを向いた。 「もうできたか。御苦労だった。…艦の周囲にまんべんなくばらまきたいんだが、操作用プログラムがまだ途中でね。配置は少し待ってくれ。…あれの使い道が何だか、わかるか」 緑は思い切って顔を上げると言った。 「違っていたらすみません。…アステロイドに打ち込んで、コバンザメの代わりにするお考えでは」 真田の顔に驚きの表情が浮かんだ。 「そのとおりだ。ヤマトをアステロイドで覆って、その中で補修作業をしようと思ってね。そうすれば皆を危険な目にあわせなくてすむからな。もちろんそれだけじゃないんだが…。しかし、どうして分かった?設計だけからは分からないと思っていたが」 「以前に古賀さんが、コバンザメを重ね貼りして作業したら、って言った時、技師長は何か考えこんでいらっしゃいました。それで…」 「そうか、顔に出てたのか。しかし、よくそんなことに気付いたな」 緑の白い頬がさっと赤く染まった。うつむいて両手で空のコップを握りしめる。その様子を見た真田は立ち上がって緑の肩に手を置いた。 「すまん、別に意味はないんだ。気にするな。…この計画に名前をつけてみたんだ。アステロイド・シップ計画っていうんだが、いい名前だろう」 緑は顔を上げ、大きな瞳をまぶしそうに細めて真田をみつめ、ほほえんだ。真田の眼がその瞳にひきつけられる。…と、その時、艦内に警報が鳴りひびいた。 『未確認飛行物体、接近!』 スピーカーから響く雪の声に、真田はきっと顔を上げた。 「しまった、もう来たのか…!」 艦橋へ行こうと部屋を飛び出す真田の背に向かって緑は叫んだ。 「技師長、アステロイドの操作プログラム、私にお手伝いさせて下さい!」 「いいからおまえは寝てこい!」 そう叫ぶと真田は走りさった。
|
|
ぴよ
2001年09月24日(月) 06時52分17秒 公開 ■この作品の著作権はぴよさんにあります。無断転載は禁止です。 |
|
| この作品の感想をお寄せください。 | ||
|---|---|---|
| アクセスする度に新作がアップされているので、びっくりです。ついついアクセス頻度が高くなってしまいます。技師長はいつアステロイドリングを開発したのか…と思ってましたが、この時だったんですね。それにしても、真田さんも長い事寝てないはず、タフだな…。 | Alice | ■2001年09月24日(月) 10時10分08秒 |